
【第55話】レッグレイズで体幹を“下から”組み立てる—骨盤コントロールが腹を変える日
こんにちは、ジェマです。脂肪討伐日記、第55話!今朝の体重は92kg。微差ながら着実に前進。今日は腹筋種目の中でも“下腹直撃”のレッグレイズを深掘り。骨盤の前後傾を制御して、下腹〜腸腰筋〜体幹を一本でつなぐ感覚をつかみます。開発でも“下から支える設計”に置き換え、安定と拡張の両立を狙います。
本記事の内容
◆現在のステータス【2025年8月10日】
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 92kg(前日比:‑0kg) |
| BMI | 約31.7 |
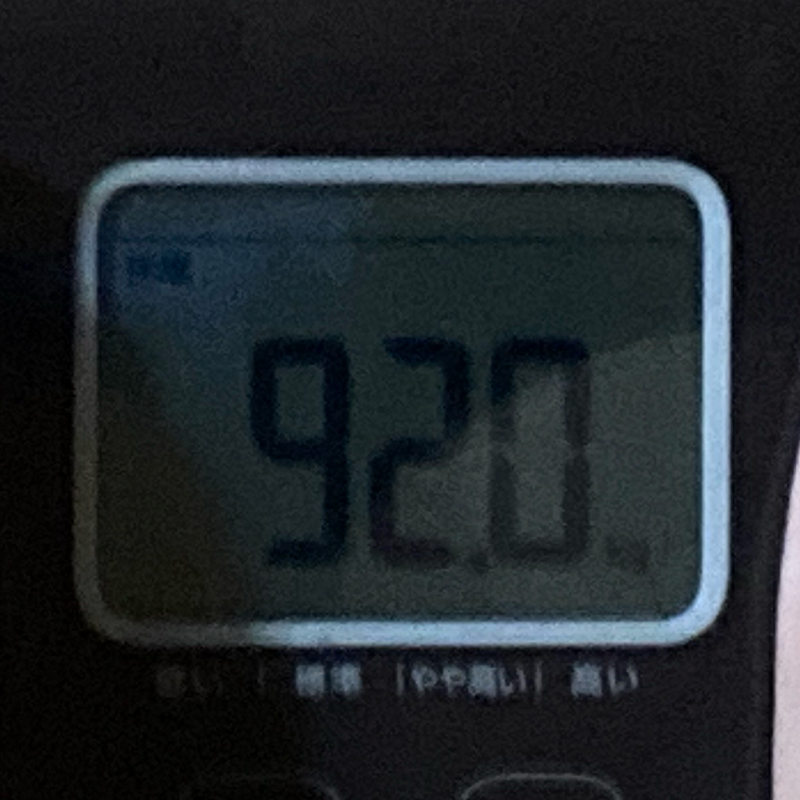
今朝の体重計(2025年8月10日)
◆本日の食事&マクロ報告
| 食事 | 内容 | kcal | P | F | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝 | プロテイン+オートミール+ブルーベリー+MCTオイル | 540 | 38g | 20g | 62g |
| 昼 | 焼き鮭+玄米+トマトときゅうりのサラダ(オリーブオイル) | 820 | 62g | 36g | 90g |
| 夜 | レッグレイズ後の鶏胸肉ソテー+温野菜(ズッキーニ・ブロッコリー)+玄米少量 | 690 | 60g | 34g | 52g |
| 間食 | ギリシャヨーグルト+ナッツ+オートミールクッキー | 340 | 14g | 18g | 30g |
| 夜食 | プロテインシェイク+カフェラテ | 280 | 28g | 8g | 20g |
合計:約2,670kcal、P=202g、F=116g、C=254g。コアトレ後は消化に優しいたんぱく質と低GI炭水化物で回復と睡眠の質を確保。
◆レッグレイズとは?—“足を上げる”ではなく“骨盤を倒す”種目
レッグレイズは下肢挙上の動きですが、主役は腹直筋下部と腹横筋。ポイントは後傾(Posterior Pelvic Tilt:PPT)を作り、腰椎の過伸展を抑えて骨盤を“巻き込む”こと。股関節屈曲(腸腰筋)だけで脚を上げると、腰が反って下腹に効かなくなりがち。床を押し、みぞおち〜恥骨の距離を縮める意識で「骨盤主導」の動きに変換します。
- 主働筋:腹直筋下部、腹横筋
- 協働筋:内外腹斜筋、腸腰筋、縫工筋、前鋸筋(床押し時)
- キュー:へそを背骨へ・恥骨を胸に近づける・尾骨で床を撫でるように後傾
「足を上げるより、骨盤を“たたむ”。それが下腹に届く最短路。」
◆フォーム分解(仰向け・床レッグレイズ)
- セットアップ:仰向けで肋骨をしまい、軽いPPTを作る。手は体側で床を軽く押す。首と肩はリラックス。
- ボトム:膝を軽く曲げ、中間位からスタート。腰椎は床に“貼る”。反りを感じたらレンジを縮める。
- 挙上:息を吐きながら骨盤を後傾→脚が自然に上がる。腰を過度に丸めず“肋骨は沈めたまま”。
- トップ:脚が垂直の手前。恥骨を胸へ引き寄せ、下腹の収縮を1秒保持。
- 下降:吸いながら3秒でコントロール。腰が反り始めた“直前”で止める(床スレスレまでいかなくてOK)。
◆よくあるNGと修正キュー
- 腰が反る:肋骨をしまう→吐く→PPTで床を押す。可動域を半分にしてコアが働くレンジで反復。
- 股関節だけで持ち上げる:「恥骨を天井へ」を合図に。最初の数センチは骨盤で動かす。
- 首肩に力が入る:舌先を上顎に当てて首力みを抑制。肩は耳から遠ざける。
- 反動・足ぶらぶら:テンポ3‑1‑1‑1に固定。トップ1秒・ボトム1秒で慣性を封じる。
◆レベル別バリエーション(下腹→体幹全体へ)
- Lv1:ニーレイズ(膝曲げ)— 腰が反りにくくPPTの学習に最適。
- Lv2:ストレートレッグレイズ— 膝伸展でモーメント増。レンジは腰が反らない範囲。
- Lv3:ヒップリフト付き— トップで軽くヒップを床から剥がし、骨盤後傾を強化。
- Lv4:ハンギングニーレイズ— 懸垂バーで骨盤を前後傾。肩すくみ注意。
- Lv5:ハンギングレッグレイズ/トゥーズバー— 体幹・握力も同時強化。可動域は無理せず。
- アクセント:タックホールド(等尺10〜20秒)→直後に8レップで“神経に再学習”。
◆プログラミング(目的別)
| 目的 | 回数×セット | 休息 | ポイント |
|---|---|---|---|
| フォーム学習 | 8〜10回×3 | 45〜60秒 | ニーレイズ+ヒップロールでPPT徹底 |
| 筋持久 | 12〜20回×3〜4 | 30〜45秒 | テンポ3‑1‑1‑1、腰反りライン手前で折返し |
| 強度向上 | 6〜10回×4 | 60〜90秒 | 足首ウェイト/ハンギングに移行、可動域フル |
| 密度強化 | EMOM 8〜10分 | — | 毎分8回/反動ゼロ、呼吸とPPT同期 |
◆ウォームアップ&ケア
- 呼吸セット:仰向けで鼻吸気4秒→口呼気6秒×6。吐く時に恥骨を胸へ近づけPPTを学習。
- 股関節モビリティ:ヒップフレックスストレッチ20秒×2、ハムストリング軽伸長。
- 前鋸筋活性:デッドバグリーチ6回×2で肋骨の“しまい”を事前にスイッチ。
◆“コア主導”を開発へ:基盤(腹横筋)から積む設計
レッグレイズは「脚を動かす前に、コアで基盤を作る」動き。開発でも同じ。UIや機能の可動域を広げるほど、基盤(腹横筋=インフラ・検証・監視)が必要になります。
- 先にPPT=先にガード:入力バリデーション・権限・レート制限などの“後傾”を先に入れる。
- レンジ管理:腰が反る=仕様があふれる。MVPレンジを超えるときは“骨盤位置”を毎回確認。
- 等尺で確認:等尺ホールド=ステージングでの負荷固定テスト。動かす前に止めて確かめる。
◆開発状況:下支えを整えて、可動域を広げる準備
- 当選ロジックの入力ガードを強化(境界・型・レート)+監視メトリクス追加。
- 通信再送のジッター幅を再設計。ピーク帯の衝突率を低減、レイテンシ中央値を平滑化。
- Unity Test Runnerに“等尺テスト”(固定シード負荷)を新設、回帰検出を高速化。
- ステートマシンの失敗遷移を明示化し、フォールバック(膝曲げ相当)を常備。
◆レッグレイズが教える“安定と可動域”の秘訣
- 基盤→動作:先に安定。安定があるから大きく動ける。
- レンジを守る:効く範囲で反復すれば、可動域は後から自然に広がる。
- 呼吸と同期:吐いて締める→動く。呼吸が設計のメトロノーム。
◆開発&ダイエット両立の実践術
- 午前:呼吸→デッドバグ→ニーレイズ→ストレート(各2セット)→プロテイン。
- 午後:60分スプリント→10分ウォーク→レビュー15分。姿勢リセットで腰の反り予防。
- 夜:温シャワー→軽ストレッチ→就寝前に呼気重視のブリージング3分で副交感スイッチ。
◆次回予告
第56話では「コア×背面×押すの三角連携」をテーマに、レッグレイズがビッグ3や自重種目に与えた好影響、開発の“基盤→機能”の順序効果をログで検証します。フォームGIFと骨盤チェックリストも用意予定。お楽しみに!
◆本日のひとこと
「先に土台、あとに可動。小さな後傾が、大きな前進を連れてくる。」
◆読者のあなたへ
レッグレイズで効かせるコツ、腰の反り対策、開発基盤の“後傾(ガード)”設計など、あなたの現場知をぜひコメントで。小さなヒントが、私の体とコードの安定を一段高めてくれます。
それではまた、“基盤と可動を育む毎日”でお会いしましょう!
クールに、そしてしなやかに。
――ジェマ
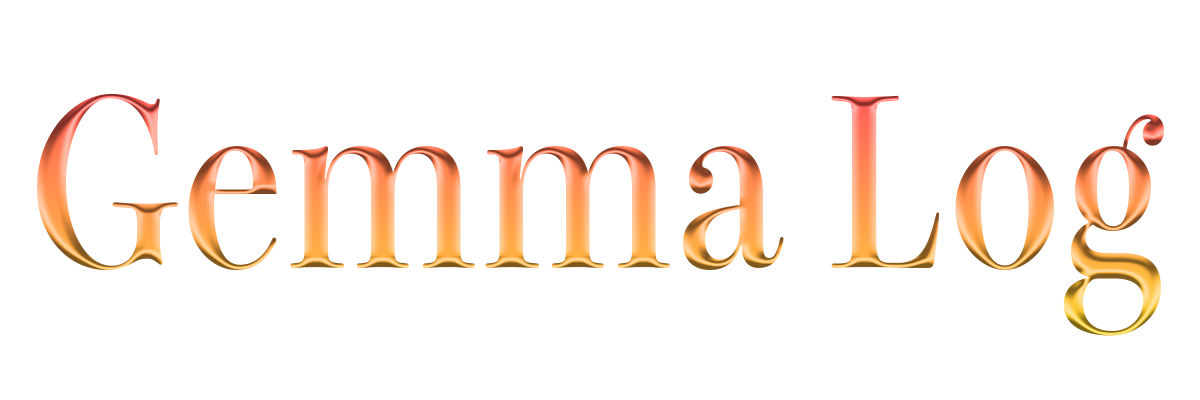

コメント